
こんにちは、不動産鑑定士の上銘です。
今回は、不動産を取得・譲渡した際に避けて通れない「土地と建物の価格の内訳」について、実務事例を交えながら整理していきたいと思います。
このテーマは、不動産会社の方、宅地建物取引士、税理士の方から数多くご質問やお見積りの相談を頂きます。
不動産売買では、消費税込みの売買代金のみで合意・契約し、土地と建物の按分は記載しない場合があります。
これは、買主は今後の減価償却を考慮して建物代金を多くしたい、売主は消費税の納税を考慮して土地代金を多くしたいといった双方の思惑があり、内訳価格の合意を得ることが難しいパターンが多いです。
| ◆ 買主 | ◆ 売主 | |
| 要望 | 建物価格を高くしたい | 土地価格を高くしたい |
| メリット | 建物は減価償却ができるため、保有期間中の利益圧縮ができる。 | 土地には消費税が課税されないため、消費税の納税負担が減る。 |
特に福岡市のように地価上昇と建築費高騰の両方が進んでいるエリアでは、土地と建物の「按分」が不明確だと、後々トラブルの原因にもなりかねません。
結論としては「不動産の個別性を反映した適正な不動産鑑定が固定資産税評価額比と乖離した場合には鑑定評価額比で按分」が令和4年の事案で認められています!
不動産取得における土地建物の按分が重要│消費税や減価償却に影響大
不動産取引において、土地と建物を一括して取得する際、その総額を土地と建物それぞれの価格に按分する作業は、消費税の納税額や減価償却費の算出に大きく影響するため、非常に重要です。
特に、収益物件のような不動産を扱う宅地建物取引士や不動産会社の方は、この内訳価格の決定方法について実務上の対応が求められます。
一般的に、土地と建物の按分方法としては「固定資産税評価額で按分」する方法が広く用いられています。
しかし、この方法は常に合理的な「時価」を反映しているとは限りません。
近年の建築費高騰や都市部における土地価格上昇といった市場の変動は著しく、固定資産税評価額と実際の市場価格との間に「乖離」が生じやすい状況にあります。
このような状況下では、納税額の適正性を巡って税務署との見解の相違が生じるケースも少なくありません。
事案から学ぶ│不動産売買における土地・建物の按分と鑑定評価の重要性
令和4年、東京地方裁判所で判決が下された消費税の更正処分等取消請求事件(税務訴訟資料 第272号、順号13726)は、この土地・建物按分の重要性の重要事案となっていますのでご紹介します。
事案の概要
| ◆ 原告(納税者) | ◆ 税務署 | |
| 主張 | 鑑定評価に基づく比率 | 固定資産税評価額比 |
| 比率 | 土地:建物=約77.30%:約22.70% | 土地:建物=約55.51%:約44.49% |
| 裁判所の判断 | ◎ (鑑定評価額比による按分が相当) | × (固定資産税評価額が時価と乖離) |
本件は、原告(納税者)が平成28年に、自身が所有していた土地と建物を一括して売却したものの、その売買契約書において、売買代金の総額は定められていたものの、土地と建物それぞれの内訳価格が明確に記載されていなかったことでその配分が問題となっています。
土地の譲渡は消費税が非課税であるのに対し、建物の譲渡は課税対象となるため、この内訳価格が消費税の課税標準を決定する上で重要な意味があります。
税務署は、消費税法施行令第45条第3項の規定に基づき、当該不動産の「譲渡の時における価額」として、固定資産税評価額を基にした比率を用いて売買代金を按分しました。
具体的には、税務署は本件不動産の固定資産税評価額比(土地:建物=約55.51%:約44.49%)を算出し、この比率で売買代金を按分して建物の譲渡対価を算定しました。
これにより、税務署は原告に対し、建物の譲渡にかかる消費税について過少申告があったとして、消費税及び地方消費税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を行いました。
これに対し、原告は税務署の按分方法に異議を唱え、更正処分の取り消しを求め提訴しました。
原告は、税務署が用いた固定資産税評価額による按分では、当該不動産の真の市場価値を適切に反映しておらず、特に土地の価値が過小評価されていると主張しました。
その根拠として、原告は不動産鑑定士に依頼して取得した鑑定評価書を提出しました。この鑑定評価に基づく比率(土地:建物=約77.30%:約22.70%)を用いるべきだと主張したのです。
原告側の主張は、この鑑定評価額比率で按分すれば、建物の譲渡対価が減少し、結果として課税される消費税額も減るというものでした。
争点と裁判所の判断│鑑定評価額比率による按分が相当
争点は、消費税法に定める「譲渡の時における価額」が、固定資産税評価額と不動産鑑定士による鑑定評価額のどちらを指すのか、という点でした。
裁判所は、同条項における「価額」とは「譲渡時における適正な時価、すなわち客観的な交換価値」であると解釈しました。
その上で、固定資産税評価額は、固定資産税の課税目的のために全国一律の基準で評価されるものであり、個別の事情が捨象されることがあるため、必ずしも適正な時価を反映しているとは限らないと判断しました。
特に、本件土地(大阪市中央区所在)の固定資産税評価額について、裁判所は、過去の地価下落期においては適時に評価額が引き下げられたものの、その後の地価上昇期には市場価格の上昇を適切に反映していなかった点を指摘しました。
その結果、固定資産税評価額が実際の市場価格(時価)と比較して「低廉」であり「乖離」が生じていると認定されました。
これに対し、本件鑑定評価では、原価法、取引事例比較法、収益還元法といった複数の手法を適用し、対象不動産の個別的要因(築年数、構造、設備、立地、周辺環境、市場の需給動向など)を総合的に考慮して適正な鑑定が行われており、特に土地の将来予測価値が適切に反映されていると評価されました。
結果として、裁判所は、固定資産税評価額比率と鑑定評価額比率との間に「実質的な差異」が生じており、固定資産税評価額による按分では合理性を肯定する根拠が失われているとして、本件鑑定評価額比率による按分が相当であると示しました。
この判決は、固定資産税評価額が市場価格から「乖離」している場合などで、不動産鑑定評価が適正な納税額を算定する上で有効な手段となることを示すものです。
まとめ│不動産鑑定評価で適正な時価を示します
上記事案が示すように、不動産、特に収益物件の売買時において土地と建物の内訳価格を決定する際には、単に固定資産税評価額で按分するだけでなく、不動産鑑定評価を検討することが有効な手段となり得ます。
鑑定評価では、対象不動産の個別的要因(築年数や物理的現況、市場の需給動向、立地等)を詳細に分析し、適正な「時価」を算出します。
建物の評価においては、経年減点補正率や減価償却、過去の修繕履歴等の考え方も考慮され、より時価を反映した鑑定評価が可能です。
特に、土地価格が大きく変動する都市部(福岡市のような地価高騰エリア)では、固定資産税路線価だけでは把握しきれない時価を適切に反映した鑑定評価で、適正な税務申告と将来的な資産戦略の面で大きなメリットとなります。
当事務所では無料で価格概算を行っておりますので、お気軽にご相談ください!
以上です。お読みいただき、ありがとうございました。
この記事の執筆者

不動産鑑定士 上銘 隆佑
Ryusuke Joumei
上銘不動産鑑定士事務所代表。
大和不動産鑑定株式会社東京本社に入社し、2019年に不動産鑑定士登録(第10401号)。国内系不動産アセットマネジメント会社への出向を経て、大和不動産鑑定株式会社九州支社へ赴任。
適正家賃、関係者間売買、証券化対象不動産、銀行の担保不動産、公有地の売買に係る不動産鑑定評価を中心に、不動産鑑定評価に携わる。
不動産鑑定業 福岡県知事 第(1)-347号
info@jkantei-office.com
お問い合わせはこちらから >
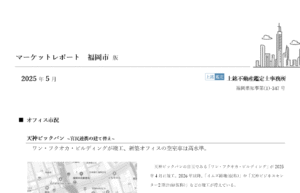

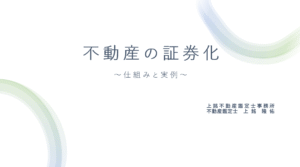
-scaled.png)
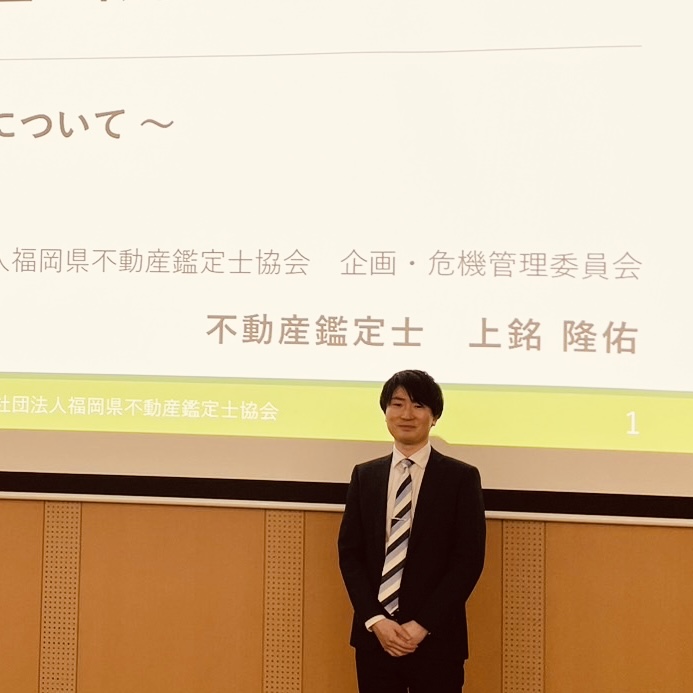
コメント